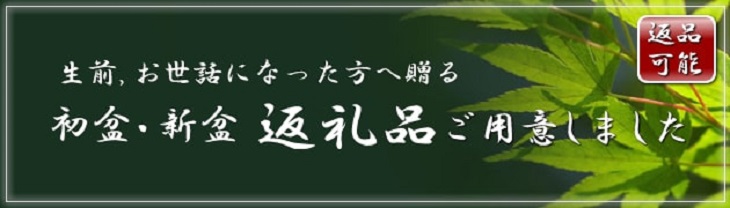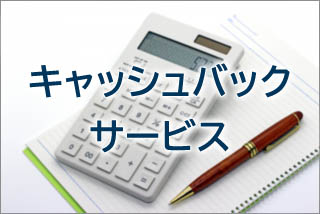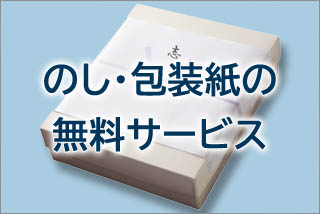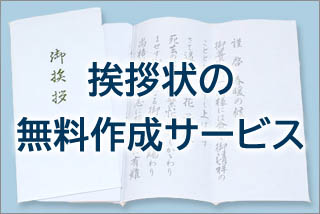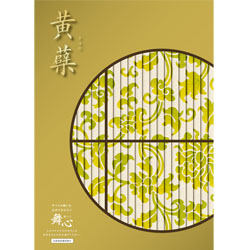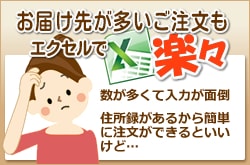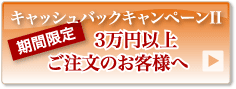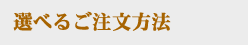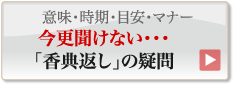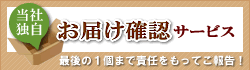香典返しのお役立ち情報
初盆・新盆の流れと準備
初盆・新盆の返礼品をご用意いたしました。以下のバナーをクリックいただくと専用ページが表示されますので、お好みの商品をお選びいただけます。
初盆・新盆について
告別式を終え四十九日が過ぎてから初めて迎えるお盆のことを「新盆(にいぼん)」又は「初盆(はつぼん)」と呼びます。
故人が仏になって初めて里帰りするということで、身内や親しい方を招いて僧侶にお経をあげてもらい盛大に供養します。また、四十九日の忌明け前に盆を向かえた場合は、新盆は翌年になります。
初盆・新盆の流れ
 |
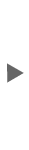 |
 |
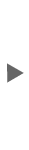 |
 |
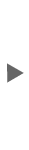 |
 |
| 施主は簡単に始まりの挨拶をします | 僧侶の読経が終わった後、ご焼香を済ませます。 | 墓地が近い場合はお墓参りをします。 | 施主のお礼の挨拶の後、会食(御斎)となります。 |
初盆・新盆の準備
お盆の時期・期間は地方によって異なりますが、7月または8月の13日から4日間行われます。| お寺への連絡 | 初盆の場合には、なるべく早く菩提寺に連絡をします。 菩提寺とは、先祖代々の墓をお願いしているお寺をさします。 霊園、墓地などを利用している御家庭では、葬儀の際に世話になったお寺に 依頼すると良いでしょう。・念のため、白提灯の供養の仕方も確認しておきます。 |
| 料理の手配 | 法要のあと会食がある場合には、料理の手配または用意をします。 仕出しなどを予約する場合には、おめでたい伊勢海老や、鯛などの献立は 避けた方がよいので、予約の際には「お盆の法事で利用します」と、利用目的を 告げましょう。 |
| 案内状の手配 | 初盆だけは、親族だけでなく知人や友人たちを招いて法要を行うのが一般 的 です。お葬式のときに記帳して頂いた会葬者名簿などをもとに案内状を出します。 また、会社関係などで執り行うお盆の法要の場合には、往復ハガキや返信用の はがきを同封した封書などで、案内状を用意し、出欠をたずねます。 |
| 引き出物の手配 | 初盆にはお参りに来られた方や初盆法要に出席していただいた方に対して引き 出物をお渡しするようにします。引き出物には持ち帰りのことを考えて軽くてかさ ばらない食品や日用品が良いでしょう。お好みの品を選べるカタログギフトはお すすめです。 |
| お布施の用意 | 僧侶にはお礼をお渡ししなくてはなりませんが、僧侶が法要のあとのお食事 (お斎)に同席して下さる場合には、御布施または御経料、お車代の2つを用意 します。もし、僧侶がお斎を辞退されたら、御布施または御経料、お車代のほか に、御膳料を加えた3つをお渡しします。 |
初盆・新盆の熨斗
のしの表書きは、「初盆」「志」「初盆志」などとし、水引きは蓮入り、蓮なし結び切り・黄白を用います。
| 初盆・新盆 | |||
| のしの種類 | のし上 | のし下 | 備考 |
| 蓮入り 蓮なし 黄白 |
初盆 志 初盆志 |
施主名・○○家 | 仏式 |
初盆・新盆のお供え物とお花の豆知識
お供え物のきゅうりとナスの意味は…先祖の霊が「きゅうりの馬」に乗って一刻も早くこの世に帰り、「なすの牛」に乗ってゆっくりあの世に戻って行くようにとの願いを込めた供え物です。

新盆のお花は…
御仏前にお供えするお花は、枕花程度の一般的なお供え花になります。色や形、お花の種類に特別決まりはありません。 亡くなってからあまり日が経っていないという配慮から、白を基調に淡い色調でまとめたご供花をお贈りすることが一般的です。