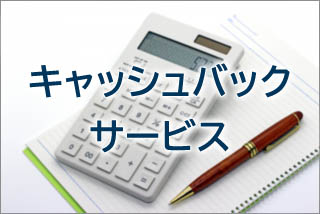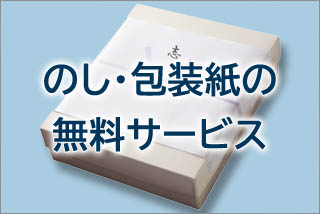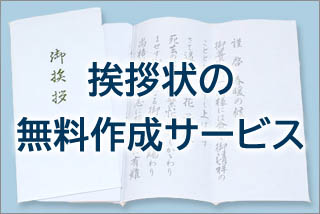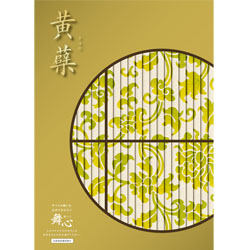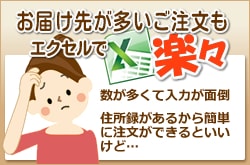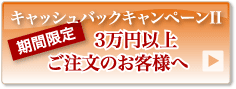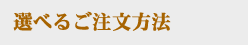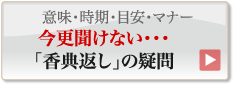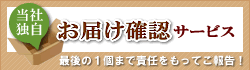仏事、法事・法要の豆知識
遺言書の種類と注意点

遺言は15歳以上の人なら誰でも書くことができます。
ただし、定められた方式に従っていないと無効になるため、注意が必要です。
遺言書は3種類
遺言書には、遺言自信が手書きする「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言の存在は明らかにしながらも、その内容については秘密にする「秘密証書遺言」があります。
自筆証書遺言
自筆証書は遺言者が必ず手書きで書き、日付と氏名の自署、押印が必要です。
ワープロ打ちや代筆はだめです。
自筆証書は手軽に作成できる反面、様式の不備で無効になる場合もあります。
また、相続させるものを具体的に書いておかないと、名義変更などの手続きが難しくなる場合もあります。故人がどこに保管していたか分からず、遺言が見つからないケースもあります。
自筆証書の遺言が見つかった場合、できるだけ早く家庭裁判所へ届け出て検認手続きを受けることが必要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人の立ち会いの下、公証人が遺言者の口述を基に遺言書を書き、遺言者、証人、公証人が署名押印したものです。
専門家である公証人が作成するため、遺言が無効になることはほとんどありません。
また、遺言書の原本は公証人が保管するため、変造や紛失の心配がなく、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。そのため、遺言執行の手続きがスムーズに進みます。
ただ、遺言の内容が証人から漏れる不安があるほか、自筆証書と比べると費用がかかります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に使います。
自筆証書と違い、ワープロ書きや代筆が可能となります。
注意点は、遺言書への署名押印と、密封した後の押印は必要で、両方とも同じ印章でないと無効になります。
また、公証人と2人以上の証人の署名押印が必要となります。
遺言書の存在は明らかになりますが、公証人が中身に関与しないため、法的不備で無効になる可能性もあります。
さらに、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所に届け出て検認手続きを受けなければなりません。
参考:知らないと損する親が亡くなったあとの手続き・相続・お金の話(白夜書房) 62ページ
3種類の遺言書を簡単に見てきましたが、いずれにせよその目的は故人の遺志を確実に反映することです。
今は健康であっても、事故や災害などで命を失う可能性は誰にでもあります。
遺産争いなど家族間のトラブルを防ぐためにも遺言について考え、作成に当たっては法律の専門家に相談することも大切です。