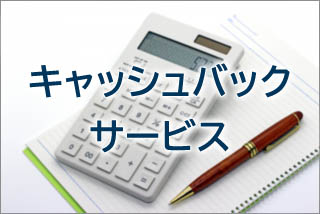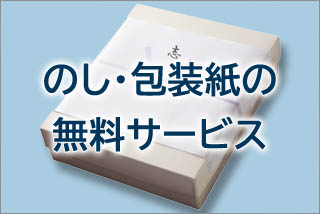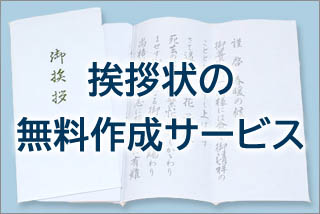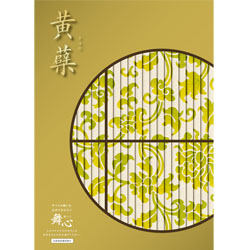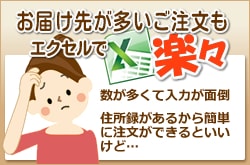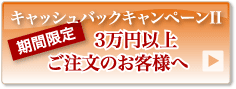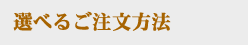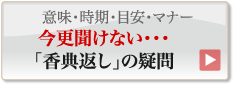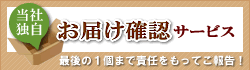仏事、法事・法要の豆知識
忌日法要、年忌法要の意味とその行い方

ここでは、故人を供養するための法要について、その意味や時期、日程の決め方、行い方などをわかりやすく解説します。死後七日ごとに四十九日まで行う「忌日(きにち・きじつ)法要」、節目となる年に行う「年忌法要」、三十三回忌の年忌法要である「弔い上げ(とむらいあげ)」について、ご紹介します。
法要とは
故人を供養するという意味の仏教用語で追善供養(ついぜんくよう)ともいいます。法要は故人を偲び冥福を祈るために営みます。冥福とは冥途の幸福のことで、故人があの世でよい報いを受けてもらうために、この世に残された者が供養をします。仏教では法要を行う日が決まっています。
忌日(きにち・きじつ)法要
忌日法要は、死後七日ごとに四十九日まで行います。
四十九日は来世の行き先が決まるもっとも重要な日で、故人の成仏を願い極楽浄土に行けるように法要を営みます。葬儀のときの白木の位牌は仮のものですから、四十九日法要までに本位牌を準備しましょう。
参考:夫が死ぬ前に妻が知っておく67のこと(伊藤綾子 かんき出版)
年忌法要
年忌法要は、一般に法事と呼ばれているもので、亡くなった翌年が一周忌、その翌年の2年後が三回忌です。三回忌からは亡くなった年も含めて数えます。一周忌と三回忌は四十九日法要に次いで大切な法要です。家族や親族のほか、故人と縁の深かった友人や知人を招いて法要を営みます。
弔い上げ(とむらいあげ)
一般的には三十三回忌で年忌法要を終え、永代供養とすることが多いようです。
最後の法要を「弔い上げ(とむらいあげ)」といいます。
また、年忌法要を打ち切るということで「年忌止め」ともいいます。
五十回忌で年忌止めとする場合もあります。
弔い上げは御祝いの意味もあり料理は精進料理を使わず、肉や魚も食されます。また、引き出物は赤の水引を使います。
参考:日本のしきたりがまるごとわかる本令和三年版(晋遊舎) 130ページ
法要の日程の決め方
法事は命日の当日に行うのが理想ですが、実際には参列者の都合もあり、最近は週末に行うことが多いです。必ず命日より早めの日に行うのが慣わしです。