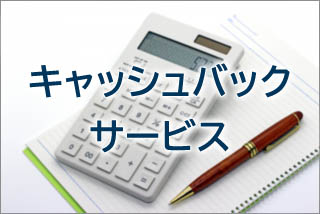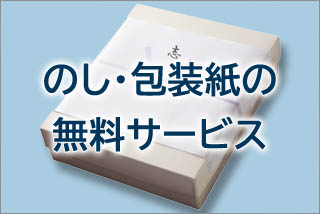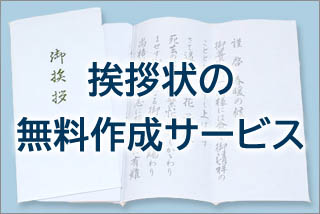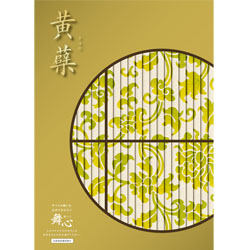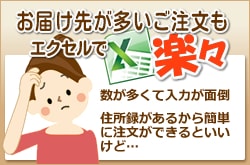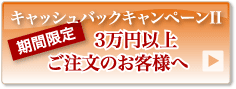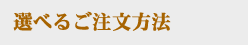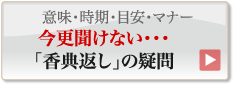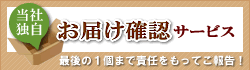仏事、法事・法要の豆知識
「数珠」「念珠」について

今回は、「数珠」「念珠」についてご説明します。
「数珠」「念珠」の由来
数珠が日本に伝わったのはは552年の仏教伝来と同時期に伝わったといいます。
奈良時代には金、銀、瑪瑙、琥珀、水晶、真珠、など貴金属、宝石類でつくられていたとか。
お釈迦様は、「木樹の実108個を通して環をつくり、常に身からはなさず、ほとけの御名を唱えなさい。
これを百回、千回繰り返し、20万辺に満つるときは、心身に乱れがなくなり、人々の心も安楽になり国家も安泰になるであろう」と言ったそうです。
数珠は百八の珠を基本として、その10倍の一千八十、また半分の五十四、その半分の二十七などの数が決められます。
これらの珠の数にも仏教的意味づけがなされています。
百八の珠は、百八煩悩に由来しますが、もともと百八という数字がインドにおいて、「非常に大きい(多い)」ことを象徴します。日本でいうところの「八百万(やおよろず)」に近い感覚でしょうか。念誦法によって煩悩を滅するという意義です。
宗派ごとの念珠
天台宗
天台宗で用いられているものは多くは、平玉です。
真言宗
真言宗の念珠は、弘法大師が唐から帰国のとき師の恵果阿闍梨に授けられといわれるものが基本形とされ、その形から振分け念珠とも呼ばれています。
またこの念珠は広く普及し、真言以外の宗派でも使われていて、八宗ともいわれます。
寺院用として54玉で造られた、半繰り念珠もあり、在家用は、形がやや小型になり、房は菊房を用いるのが一般的です。
浄土宗
浄土宗とここからでた時宗は、多く輪違いの念珠が用いられています。
これは、法然上人の門人、阿波之助が考案したといわれています。
のちに、称念が現在のように改作したものといわれており、2つの輪違いのものに丸環がつけられていて、一般に日課数珠と呼ばれており、日課念仏に用いる繰り念珠です。
この日課数珠には、108個の数珠10連を合わせて1080個の大きさにしたものもあり、百萬遍大数珠といわれている。装束念珠は、基本形がやや異なっていて、在家用としては、片手じゅずが現在多く用いられています。
浄土真宗
真宗の念珠は、中興の祖、蓮如(れんにょ)上人の考案になるもので、基本形は浄土宗と同じですが、裏房の結び方がこの宗派独特のもので「蓮如結び」といわれています。
かた、形式は同じですが、「兼朝用」・「布教用」といわれる特殊なものもあります。
在家用のものも、基本は同じですが、これが簡略されて、寸法で決められていて、玉の数には制限がないのが特徴です。この他、一般的な片手念珠も用いられています。
日蓮宗
日蓮宗の念珠は、宗祖日蓮上人以来、華厳宗などの南都六宗で用いられている古い形式のものを使用していましたが、室町末期頃より現在の形のものも用いられるようになったといわれています。
以後、広く日蓮宗各派に用いられる基本形となり、顕本法華宗、仏立宗、などの各派、祈祷用の各種のものなど、房の組み方の違いがみられるぐらいです。
在家用のものも基本はすべて同じです。