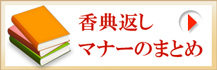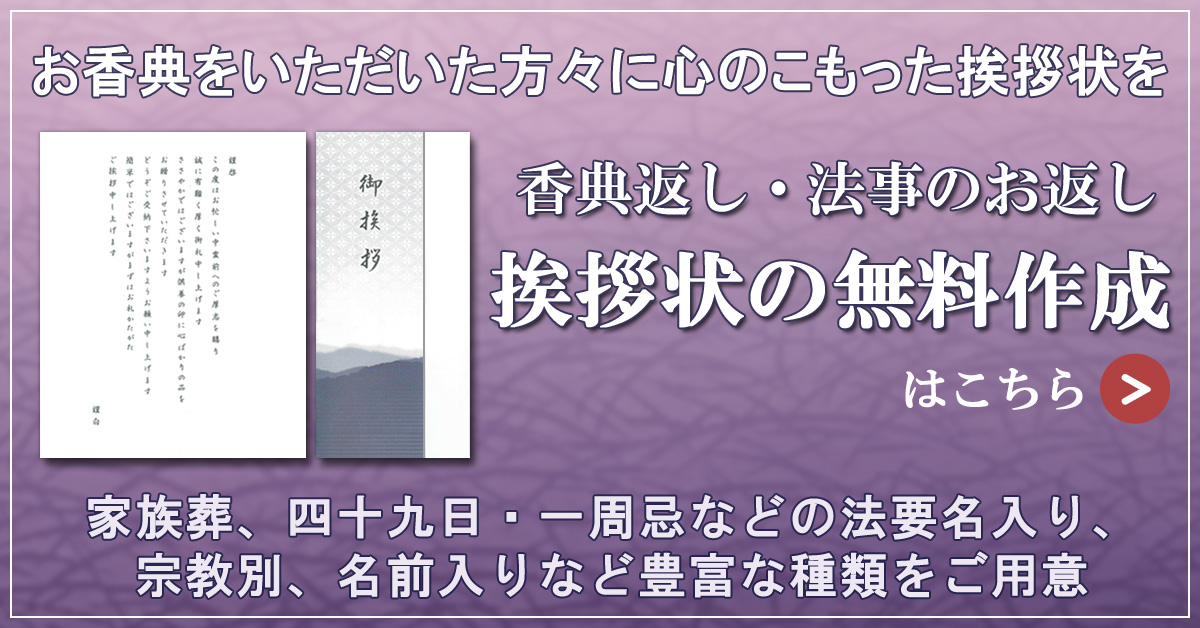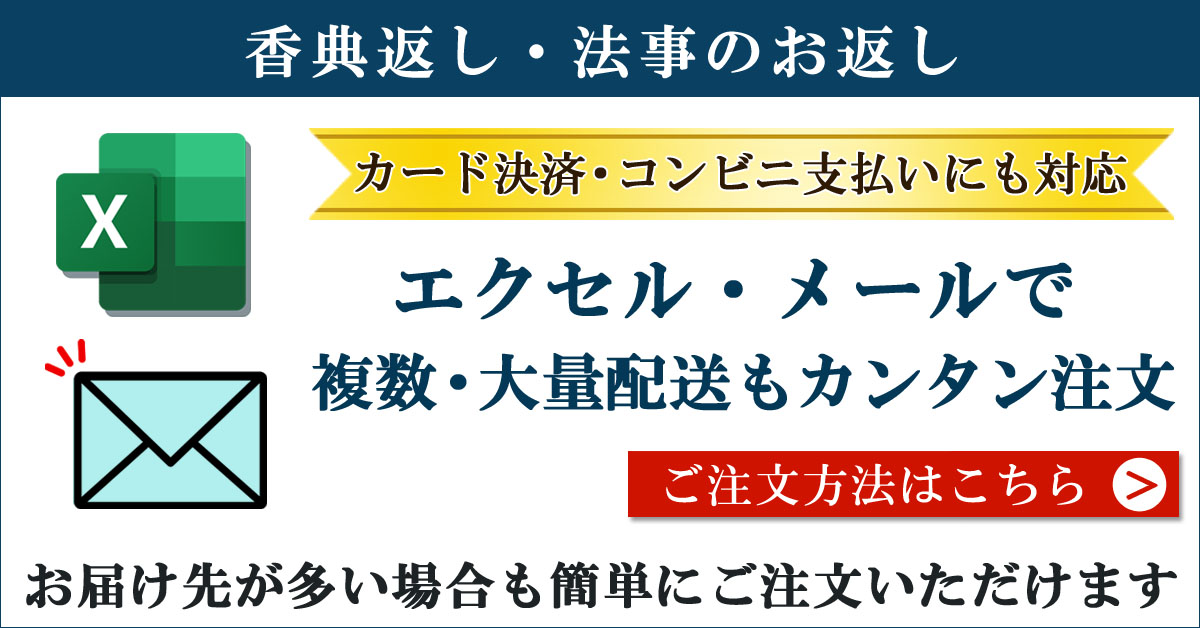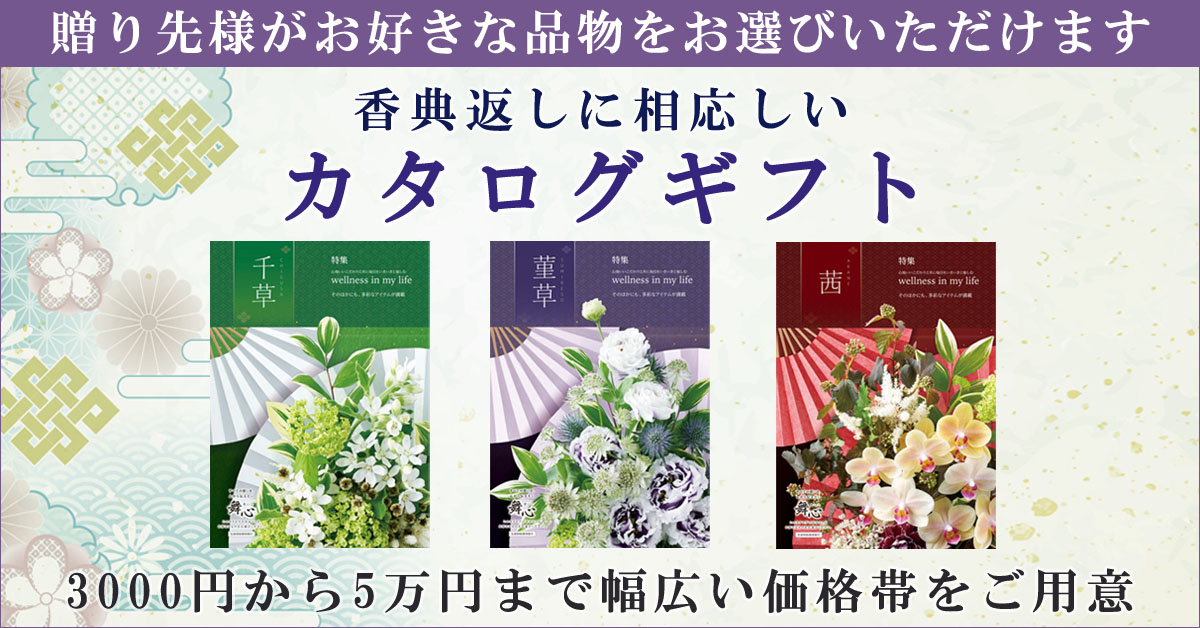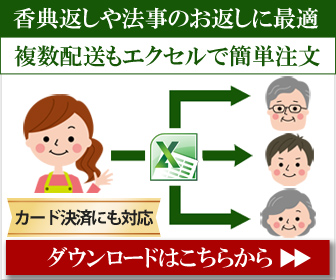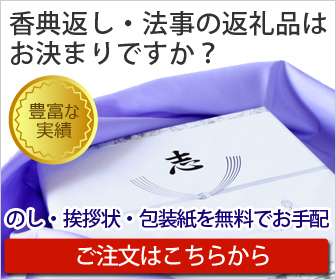葬儀・葬式や告別式のとき、弔問に来られた方から香典をいただきます。香典をいただいたら、感謝の気持ちを込めて香典返しを贈ります。香典返しのしきたりは宗教や地域によって異なりますが、ここでは、仏式で葬儀を行った場合の一般的な香典返しの方法について紹介します。
葬儀・葬式や告別式のとき、弔問に来られた方から香典をいただきます。香典をいただいたら、感謝の気持ちを込めて香典返しを贈ります。香典返しのしきたりは宗教や地域によって異なりますが、ここでは、仏式で葬儀を行った場合の一般的な香典返しの方法について紹介します。
目次
葬儀・葬式のお返し「香典返し」の始まりは?
不幸があったら「香典」を渡す風習は古くからありましたが、お葬式のお返しとなる「香典返し」は比較的新しい習慣といわれています。
村や集落などの共同体の繋がりが強かった時代は、不幸があった家に近所の人が香典としてお香や農作物などを持ち寄り、葬儀のお供えや食事に充てていました。不幸があった家は誰から何をどれだけもらったかを記録しておき、もらった家に不幸があったときに同じ分だけ返すという仕組みになっていました。
しかし、時代の流れとともに共同体の繋がりが弱まり、村から引っ越す家も出てくるようになると、もらったものを次の機会に返すことが難しくなってきます。そこで、葬儀で香典をいただいたらその都度返すという香典返しの風習が生まれたといわれています。
カタチは変わっても「葬儀の際にいただいたものにはお返しをする」という考え方は、今も昔も同じといえます。
葬儀・葬式のお返しの目安は半返し
香典のみをいただいた場合
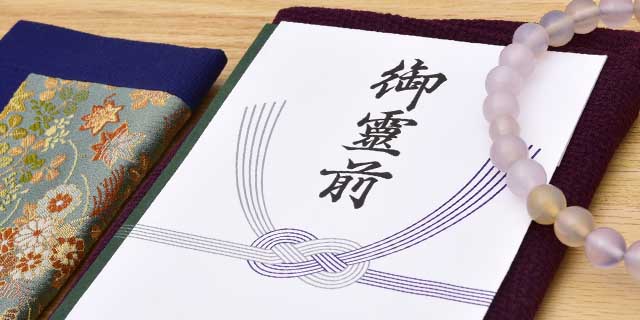
香典返しをするときは「半返し」といって、いただいた香典の3分の1から半分を目安にお返しをするのが一般的です。仮に1万円の香典をいただいた場合は、5000円のお返しの品物をお贈りします。
一説によれば、昔は今ほど葬儀にお金がかからず香典の半分ほどが残ったため、それをお返しに充てたことが半返しの由来とされています。
お供え物をいただいた場合は?

香典以外にも親族などからお花や果物、お菓子などのお供え物をいただくことがあります。
香典とお供え物をいただいた場合は、合計額をもとに考えるとよいでしょう。たとえば、香典を1万円、お供え物を5000円分いただいたような場合、半返しだとすると7500円くらいの品物をお返しすることになります。
また、3000円相当のお供え物のみをいただいた場合には、香典返しの通販ショップであれば、送料込みで1500円程度の品物でお返しができます。
それよりもさらに低額のお供え物のみをいただいた場合は、手紙やお礼状で無事葬儀を終えたことと、感謝の気持ちをお伝えするとよいでしょう。
お花へのお返しに関する詳しい内容は、以下の記事をご参照ください。
弔電をいただいた場合は?
事情があって葬儀に参列できず、弔電をいただくケースもあります。弔電のみの場合は、お返しの品物は必要ありません。
ただし香典ももらった場合は、他の香典返しと同様にお返しをします。
弔電をいただいた場合の詳しい内容は、以下の記事をご参照ください。
参考:増補改訂版身内が亡くなった時の手続きハンドブック(奥田周年 日本文芸社) 87ページ
葬儀・葬式のお返しを行う時期は?

本来は四十九日法要後
香典返しは、本来のしきたりでは四十九日法要のあとに贈ります。
喪家にとって四十九日は「忌明け」であり、通夜・告別式から続いた弔事が一段落する時期です。そのあとに、いただいた香典の半返しを目安に香典返しを贈ります。
また、四十九日の法要後に香典返しを贈る場合は、忌明けの報告を兼ねた挨拶状を添えるのが一般的です。
当日返し
四十九日法要の後ではなく、葬儀の当日に香典返しをすることを当日返しといいます。
法要後の香典返しでは香典額に応じた香典返しを用意できますが、当日返しではそれができませんので、2000円や3000円といった一律の品物を用意することになります。
そのうえで高額な香典をいただいた場合は、四十九日法要後に改めて香典返しを贈ります。例えば、3万円の香典をいただき、当日返しに3000円の品物を用意していた場合、半返しであれば12000円相当の品物を改めて贈ります。
香典返しの時期について、以下の記事もご参照ください。
参考:配偶者が亡くなったときの手続き・葬儀・相続のすべて(曽根恵子 PHP研究所) 52ページ
葬儀・葬式のお返しにふさわしい品物は?

葬儀・葬式のお返し(香典返し)の品物は、不祝儀をあとに残さないという意味で「消えてなくなる物」がふさわしいとされています。そのため、日本茶やコーヒー、紅茶、洋菓子、和菓子、乾麺、乾物などの飲み物や食品がよく選ばれています。洗剤やタオルなどの日用品も消耗品のため香典返しに適した品物です。
四十九日法要後の香典返しと当日返しの品物の選び方は基本的には同じですが、当日返しの場合は持って帰っていただくことになりますので、重いものやかさばるものは避けたほうがよいでしょう。法要後の香典返しでは、相手に好きな物を選んでもらえるカタログギフトも人気があります。
参考:親の葬儀とその後事典 : 葬儀法要・相続・手続きのすべて(黒澤計男、溝口博敬 法研) 86ページ
お返しののしの表書きは?
お返しの品物は、弔事用の包装紙とのし(掛け紙)で梱包します。
「志」や「満中陰志」の表書きののしを掛け、香典返しの品物と相手に伝わるようにします。
のしや表書きなどについては、以下の記事をご参照ください。
参考:新装版短いスピーチあいさつ実例大事典文例1500(主婦の友社) 22ページ
まとめ
・葬儀・葬式で香典をいただいたらお返しをする
・葬儀・葬式のお返しの目安はいただいた香典の半返しが一般的
・お返しの時期は四十九日法要後が本来のマナー
・葬儀・葬式のお返しの品物は「消えてなくなるもの」がふさわしい
著者情報

- 当サイトは香典返し・法事の返礼品の専門店「香典返しe-shop」が運営しています。当店は長年にわたり、お葬式や法事の返礼品を通して、全国各地の数多くの喪主様や施主様、ご遺族のサポートを行ってまいりました。当サイトでは、これまで培ってきた経験をもとにお葬式や法事のマナーに関する情報を分かりやすくお伝えしています。
- 2025年3月20日香典返しのお役立ちガイド香典返し 洗剤の選び方や人気の洗剤セットをご紹介
- 2025年3月17日香典返しのお役立ちガイドいまどきの香典返しの人気ギフトは? 重視される点や選び方について
- 2023年4月13日香典返しのお役立ちガイド香典返し コーヒーの選び方やおすすめのコーヒーセットをご紹介
- 2023年3月24日香典返しのお役立ちガイド高齢者向けの香典返し、商品の選び方やマナーについて